
- 著者:
- 寺田寅彦
- 朗読:
- 平川正三
物理学者でもあり、様々な著作を発表した寺田寅彦が帝国大学学生に向けて書いた作品です。ノーベル物理学書、科学賞など日本の科学の礎になった時代の学生に向けたメッセージです。現代に再度この心を見直す機会になれば良いと思いながら刊行いたしました。
オーディオブックのことなら名作・名著を文芸から一般・学術書まで提供することのは出版オーディオブック。日本の心シリーズ、文豪、時代小説など脳を健康にするオーディオブックを揃えています。

物理学者でもあり、様々な著作を発表した寺田寅彦が帝国大学学生に向けて書いた作品です。ノーベル物理学書、科学賞など日本の科学の礎になった時代の学生に向けたメッセージです。現代に再度この心を見直す機会になれば良いと思いながら刊行いたしました。

人の心の複雑さと闇を多面的にドラマチックに表現したこの作品は、黒澤明が映画「羅生門」で描き、世界的に有名な短編となった

文身とは入れ墨のこと。『文身自慢の會』趣向を凝らした文身のなかに現れた美男美女、いずれ劣らぬ見事な文身だが・・ 親分とガラッ八の彫り物もご照覧あれ

奇跡のお地蔵様。泡食ってるガラッ八。消えた千両箱。縛られ吊るされた娘。「どうしたッてんだ。地蔵様が踊り出したとでも言ふのか」平次の炯眼が光る!

神田・日本橋界隈で花嫁が次々と祝言の晩に行方知れずに。平次もこれはと乗り出すが、曲者にまんまとしてやられてしまう。お静を囮にしかけるが・・・

百樽もの毒薬が消え失せ、なんとしても見つからないまま数年が過ぎ——「親分、大變ツ、落着いて居ちやいけねえ・・・・みなごろしにされたんですぜ」

火付盗賊改方の小野十蔵はあまりに無口なために、その姓をもじって、同僚から「唖の十蔵」などと呼ばれているがその働きは抜群のものであった。
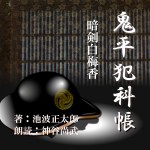
会津屋敷の切れ目の掘割りに小さな橋がかかってい、平蔵が、これをわたりかけたときであった。背後から、突風のように肉薄して来る殺気を感じた。

紫色の斑点がいくつも浮き出して見える。これは、まさに彦の市以外の男の唇が、彼女の肌を吸った痕なのである。(畜生め、ほかに男を……)

若かりし日、〔本所の鏡〕こと平蔵をヒモとしていたおろく。そのおろく、おもんを助手にして「新しい仕事」をやりはじめた。

貝柱の〔かき揚げ〕を浮かせたそばをやりはじめ、(む……うまい) 否応なしに舌へ来る味覚と同時に、またも、(あの男、どうも、くさい・・・)

「こうなれば押しこみ強盗でも……」という気持になるのもむりはないところだが、さすがに〔忠さん〕そこまでは落ちきれぬところがある。

長谷川平蔵が〔その女〕をはじめて見たのは……あの組下同心。木村忠吾が、まだ谷中いろは茶屋の娼婦お松のもとへ通いつめていたころのことだ。

巧みな声色を遣って押し込み、金品ばかりか娘や若い女房などを次々に犯すという押し込みが頻発する。

「いいかい、弥市どん。お前、気をつけねえよ」「え‥‥‥!」「縄ぬけの源七どんが、江戸へ帰って来たぜ」

大滝の五郎蔵は、脱獄というかたちをとって娑婆へでた。
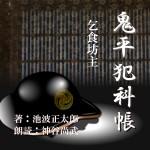
押し込みの繋ぎをつけていた惣介と鍋蔵は、縁の下にいた乞食坊主に密談を聞かれてしまう。

風邪で寝込んだ平蔵の寝間から愛用の銀煙管が盗まれた。不覚を取った平蔵が鮮やかな逆転を見せる。愛読者人気ナンバーワンの作品。
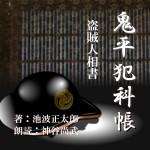
盗賊の似顔絵を描いた石田竹仙は、達者な筆運びで絵を仕上げたが、なぜか描き終えたときには、疲れきって口もきかぬようになってしまった。

旅の老武士が笠をぬぎ捨て、懐から出した革紐を襷にまわしかけ、震える手でよれよれの鉢巻をしめ、大刀を引き抜くのを、石灯篭の陰から平蔵は注視した。