
- 著者:
- 野村胡堂
- 朗読:
- 後藤敦
「親分、子さらいが流行るんだってネ」八五郎が噂する間にも、また一人。「俺の縄張うちへ来ちゃ放っておけまい」しかしこのたびの件は、流行りの人さらいとは様子が違います。
オーディオブックのことなら名作・名著を文芸から一般・学術書まで提供することのは出版オーディオブック。日本の心シリーズ、文豪、時代小説など脳を健康にするオーディオブックを揃えています。

「親分、子さらいが流行るんだってネ」八五郎が噂する間にも、また一人。「俺の縄張うちへ来ちゃ放っておけまい」しかしこのたびの件は、流行りの人さらいとは様子が違います。

「お政が来たはずじゃないか」「でも、それは勘定に入らないでしょう。殺された人ですもの」「なるほど、そう言えばその通りだ」・・平次は謎めいた言葉とともに苦笑します。

「この下手人は、三輪の兄可が晩んだ板倉屋でもなきゃ、名乗って出たお前でもないのさ。まアまア俺に任せておきな」細工は流々仕上げを御覧じろ、の平次であります。

「――不景気と言や、親分、近頃銭形の親分が銭を投げねえという評判だが」とはガラッ八の減らず口。・・お待たせしました。平次の颯爽たる投げ銭の技、お楽しみください。

「それでも文句を言うなら、結納の代りだとか何とか、いい加減な事を言って、これを見せるがいい」平次は何やら風呂敷に包んだ品をガラッ八に持たせ、策を授けるのでした。

「親分、驚いたぜ、――御用間がなぐり込みの片棒をかつぐなんて」「シッ、黙っていろ、――これは御用間の仁義さ。」平次の慧眼と男気、ガラッ八とのかけあいの光る一作です。

男の左手小指から中指までが焼けて掌に貼りつき折れ曲がったままになってしまっている。雨の夜に澪通り木戸番小屋に転がり込んできたのは、南組三組の纏持ちだった勝次だった。
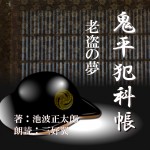
蓑火の喜之助の運命をかえた女おとよは、麦飯・とろろ汁・川魚料理などが名物として知られている山端の茶屋「杉野や」の茶汲女であった。

鈴鹿の又兵衛は、右腕である梅原の伝七と、栗飯にとうふの汁、甘鯛の味噌漬けなどをつつきながら[おさめ金]を用意するための急ぎ盗の相談をした。

死を覚悟した万五郎のとほうもない打ち明け話に、妾のおけいは生きた心地もしなかった。逆に万五郎はめずらしく食欲を出し、卵をおとした熱い粥を食べた。

中村宗仙は、京都は東寺の境内にある茶店〔丹後や〕で、お八重を目にとめた。「後家でございます」と言った女は、実は大阪の香具師の親分・白子の菊右衛門の妾だった。

天満宮・表参道にならぶ料亭と同じく、菜飯と田楽を売り物にしている風雅な料亭〔紙庵〕に、忠吾と女が入ったのを、長谷川平蔵はつきとめている。

保津川や清滝川でとれる鮎が京に運ばれる途にある愛宕山〔平野や〕の鯉、そのうす紅色のそぎ身が平蔵の歯へ冷たくしみわたった。が、骨休めもほんのひとときのことであった。

宇津谷峠の上り口に、小さなだんご十個を一連にして麻の緒でむすんだ〔十だんご〕を売る茶店がある。それと竹の水筒に汲ませた岩清水を伴に、平蔵は左馬之助を待った。

「この餓死をしかけている老婆へ、熱い粥などを見せながら、責めつけて見れば、みんな吐くさ」きびしく巧妙な長谷川平蔵の追及のはじまりである。

早くに親を亡くした〔小川や梅吉〕〔霧の七郎〕兄弟は幼い頃から仲がよく、兄が与えてくれた沢庵飯を七郎は今もたまらないなつかしさで想いおこすほどであった。

木村忠吾が久しぶりに会う叔父・金森与左衛門と、目黒不動堂惣門前の料理茶屋〔稲葉屋〕で酒を飲みつつ豆腐の田楽をつついていると、叔父がふしぎなことをもらした・・

自慢の〔芋膾〕を喜び女房の土産にまで詰めさせた〔浪人さん〕のあとをつけ〔鬼の平蔵〕であると悟って、鷺原の九平はぞっとした。腰を抜かすほど驚愕した。

蕎麦やへ火をつけ金を盗み逃げたとして、相川町の菓子屋〔柏屋〕の奉公人・亀吉が挙げられた。その亀吉が〔晒しもの〕にされているのをながめ見て、平蔵の胸がさわいできた。

佐嶋忠介は馴染みの店、芝・神明前にある〔のっぺい汁〕が名物の料理屋〔弁多津〕で目を覚ました。二千石の大身旗本・横田家嫡子誘拐犯の定めた日は、今日である。